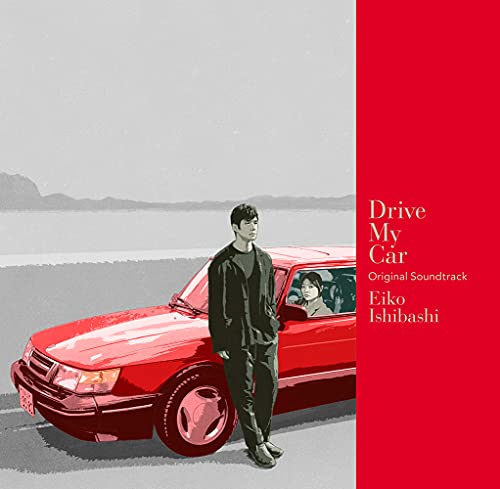悲しいフリはもう止めて 『ドライブ・マイ・カー』

2020年の年の瀬。新型コロナウイルスが第三波として猛威を奮い始めた頃、私はある海沿いの大学病院で緑内障の手術を受けた。緑内障の手術というのは、一定以上高くなってしまった眼圧がこれ以上高くならないようにする為の〝現状維持〟の手術であることが多い。眼圧が高くなることで視野が失われてゆき、酷ければ失明する可能性もある。そうした結果にならない為に行うものであり、視力/視野が回復する手術ではない。
チェーホフの代表的な戯曲『ワーニャ伯父さん』には、以下のような台詞がある。
人生は失われた、もう取り返しがつかない──そんな思いが、昼も夜も、まるで家の悪霊みたいに、ぼくの心をさいなむんだ。
今から約120年前の、47歳を迎えた中年男の喪失の感覚を、別の喪失の感覚と重ね合わせたのが濱口竜介の新作映画『ドライブ・マイ・カー』である。
■観客のいない演技
村上春樹の同名短編小説が原作となってはいるが、同作が収録された短編集『女がいない男たち』に併録の『シェラザード』『木野』からもモチーフを拝借して、濱口はほとんどオリジナルに近い新たな『ドライブ・マイ・カー』を作り上げた、という例えの方がしっくり来る様に思う。
演劇を生業とする夫婦がいた。妻は夫に隠れて共演者と浮気を重ねていた。夫はその事実に気付きながら気付かない〝演技〟を続けた。だが妻は「話がある」と出がけの夫に告げたまま、その晩に還らぬ人となる。簡単に説明するならこんな映画である。
残された夫:家福(西島秀俊)は、妻:音(霧島れいか)の死から二年後、広島のとある演劇祭に招聘され、演出家として『ワーニャ伯父さん』を手がけることになるが、そのオーディションには妻の浮気相手の若い男:高槻(岡田将生)という俳優も応募していた。ここまでが大体の序盤の見せ場となっている。
家福は、高槻に対しても、亡き妻:音が彼と逢瀬を重ねていたことを全く察知していなかったかのような〝演技〟をする。原作小説には、妻の浮気に身を焦がしながら以下のような独白をしたりもする。
でも家福はプロの俳優だった。生身を離れ、演技をまっとうするのが彼の生業だ。そして彼は精いっぱい演技をした。観客のいない演技を。
演技を生業とするような人間が「僕を深く愛すると同時にごく自然に僕のことを裏切っていた」〝そんな妻の死〟という現実にどう向き合うのか。映画版『ドライブ・マイ・カー』で描かれているのはそうしたテーマであるように思う。
■喪失と獲得 主人と従者
未然の状態から何かを得る感覚と、今までそこにあることが当然であった物や人を失う感覚があるとして、そうした〝振り〟をするのはどちらが簡単だろうか?私個人の話で言えば、緑内障によって視野のかなりの部分が失われ、もう右目だけで活字を読むことが困難な状態になった。右目が左目の〝添え物〟にでもなったような感覚である。手術の半年前には全く想定していなかった事態だった。そうしたことを考えれば、未然の状態から「何かを得ること」を想像することと、「何かを失うこと」を想像すること、それを用いてその振りをすることは、どちらの演技がより技巧を必要とするだろうか(ここまでで書きそびれたが、劇中の家福もまた、緑内障の進行を予期せぬ形で医者から告げられる)。
映画の中盤には、演劇祭が家福専属のドライバーとして雇い入れた、みさき(三浦透子)という女性が登場する。後半に明かされることだが、「妻の死」という大きな喪失を抱えた家福と同様、彼女もまたある種の喪失を心に秘めている人物であり、この二人は多くの非・演技状態、いわゆるオフステージの状態を、車内で共有することとなる。二人にとっては、車外の空間は全て〝舞台〟であり、家福の愛車:サーブ900の限られた密室は気心の知れた共演者の控え室的な役割を果たしている(車外は全て舞台、と前記したが、車外で二人が親交を深める印象的なシーンも複数登場する)。
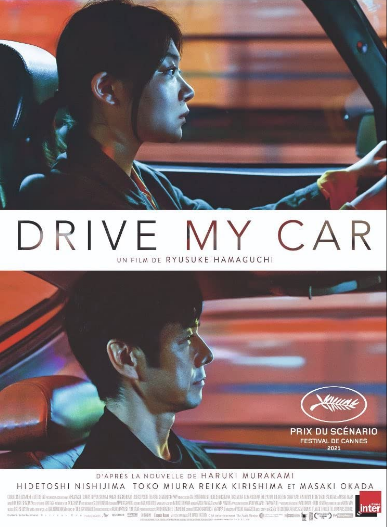
予め身を差し出すことが大前提となっている忠実な従者と、その有能な技術に全幅の信頼を寄せる主人。そんな二人の関係は、立場が対等ではない者同士の、言い換えれば対等ではないからこその、奇妙な信頼関係を帯びてゆく。そしてそれは、物語の終盤の非常に重要な場面で、二人の関係を『ワーニャ伯父さん』における終幕直前のワーニャとソーニャの関係に重ねているシーンで遂に〝対等〟となる。
■女を失う男たち 喪失を演じること
村上春樹の『シェラザード』の中には以下のような一文がある。
しかし羽原にとって何よりつらいのは、性行為そのものよりはむしろ、彼女たちと親密な時間を共有することができなくなってしまうことかもしれない。女を失うというのは結局のところそういうことなのだ。現実の中に組み込まれていながら、それでいて現実を無効化してくれる特殊な時間、それが女たちの提供してくれるものだった。
性的関係を共有する親密なパートナーに何を求めるかによって異なると思うが、男性が女性へ抱く想いとして、私の感覚で言えば、上記の例えに異論は無い(女性が男性へ、ではまた大きく異なりそうな気がする)。監督である濱口竜介も、本作について「女性に去られるということは男性の根源的な恐怖」と語っている。
『ドライブ・マイ・カー』の家福を捉え続けるのは、用意しながらその封を永遠に閉じつつこの世からいなくなってしまった妻:音が「最後に伝えようとしていたこと」である。
『木野』には、妻が浮気をした末に離婚をすることになった語り部の木野が、妻から以下のような問いかけをされるシーンがある。
「傷ついたんでしょう、少しくらいは?」と妻は彼に尋ねた。「僕もやはり人間だから、傷つくことは傷つく」と木野は答えた。でもそれは本当ではない。少なくとも半分は噓だ。おれは傷つくべきときに十分に傷つかなかったんだ、と木野は認めた。
映画『ドライブ・マイ・カー』の予告でも象徴的に引用される「僕は正しく傷つくべきだった」という家福の言葉は、上記の木野の心情の再構築と言える。そして、木野の職業は役者ではないが、ここでも前記の〝演技する〟という感覚が重要な意味を成している。
自分の愛する女を、男が失うということ。それは悲しいことだろうか?それは男が涙を流してオイオイと泣くことだろうか?そもそもこういう局面に陥ってオイオイ泣けるような男は、こんなことを考えすらしないであろう。
つまり、「有害な男性性」であったり「男らしさから降りる」と言った物語は、ここ何年かで世の中に顕著に出回るようになった気がするが、そこに共感することができるような感覚の男性こそが、いざ自分の身にそうした〝喪失〟が降りかかると、なんてことはない、これが人生だ、男と女の関係には絶えず付かず離れずが存在するのだ、それが当たり前なのだ、特に悲しいことではない、自分より不幸な人間は山ほどいる、「なんてことはない」と自身の感情を偽り〝喪失の演技〟をしてしまうことはないだろうか?
映画の最後で家福は、もう喪失を演じる必要はない、という答えに辿り着き、それまで避けてきた『ワーニャ伯父さん』と再び対峙することとなる。ソーニャがワーニャに訴える「ワーニャ伯父さん、生きていきましょう。長い長い日々を、長い夜を生き抜きましょう。運命が送ってよこす試練にじっと耐えるの。」という言葉は、オプティミズムだろうか。それともニヒリズムだろうか。あるいはそれらの概念を理解していない者の口から出た、嘘偽りない感情を乗せた言葉だろうか?
劇中でみさきが高槻のことを「嘘をついているようには思えない」と喩えたように、病気によって視力の喪失を経験した私にとっては、チェーホフがソーニャという鋳型に託した言葉も、家福がユナ(パク・ユリム)という俳優の韓国手話を通して発した言葉も、「嘘をついているようには思えない」のであった。

海沿いの病室から片目で眺めた海は、今まで見たことがないほど穏やかだった。